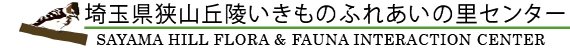ハチ?チョウ?カノコガ~ふれあいの里だより令和6年6月号~
梅雨入りが気になる6月、ヨーロッパでは心地よい西風が吹く季節です。日本ではこの西風に由来するゼフィルス、ミドリシジミの仲間たちが年に一度発生する時期になります。
この時期に発生するものにカノコガもいます。大きさも飛び方も見つけやすく、ガは区別がつきにくいものが多い中、見わけも付きやすい身近な昆虫です。
カノコガは北海道、本州、四国、九州の平地、山地に普通に生息するヒトリガ科のガです。6月から9月に発生し、昼間活動します。ヒトリガは漢字では火取蛾で、多くの仲間に走光性があり光に集まる習性からついています。まさに飛んで火に入る夏の虫といったところですがカノコガには当てはまらないようです。翅を広げると30mmから37mmで、様々な花で吸蜜します。
半透明の翅が鹿の子模様のように見えるところから名前が付きました。細い前翅に極端に短い後翅、黒い胴体に二本の黄色い縞模様と言った姿はオオフタオビドロバチやキオビツチバチに擬態していると考えられています。
幼虫は黒い毛虫状で毒はなくシロツメクサ、スギナ、ギシギシ、タンポポなどの葉を食べます。幼虫で冬を越し、成虫は6月ころに第1化が、8月ころに第2化が発生し、この後生まれた幼虫が冬を越します。羽化すると一部の鱗粉を落とし半透明の翅になります。これもハチに似せているのではと考えられます。
6月の第1化を目にすることが多く、昼間低い位置をゆっくりと飛び色々な花に来るので見付けやすく捕まえるのも簡単です。交尾しているところにもよく出会います。そっと近づいて観察してみてください。胴体の太い方がメスです。
よく似たキハダカノコは胴体がその名の通り黄色地に黒の縞模様なので区別がつきます。また、石垣島、与那国島にはムラマツカノコがいますが、翅の模様が少し複雑で、胴体に二本の黄色い線のほかに、首の後ろに黄色い線が1本入ります。日本にいるカノコガの仲間はこの3種ですが、世界には数千種いると言われ、亜熱帯から熱帯地方に多く、特に南アメリカには多くの種数がいます。いずれもその地域にいるハチなどに擬態していると思われ派手なものが多く見られます。
カノコガの学名はAmata foruneiで、種小名のfortuneiは「fortuna」で、運・運命・幸運・機会・財産などの意。なんだか出会えたらラッキーな感じがします。
翅を触ると鱗粉が、指に翅の鹿の子模様が判を押したかのように付くところから『ハンコチョウ』という別名もあります。ハチに擬態しているようで、チョウのようにも見えるカノコガです。
深緑の中、姿は見つけにくいものの、ひときわ野鳥たちの声は印象的に響き渡ります。親鳥は2回目以降の子育て中のものが多く、シジュウカラは若鳥で小さな群れを作っています。
花は少なくなりましたが、ムラサキシキブの良い香りが森に漂います。ニワトコの実は赤く色づき、5月に咲いていたカマツカやマユミも若い実をつけています。
今年は6月21日が『夏至』で、北半球では一年で最も昼の時間が長い日です。埼玉での日の出は4時25分、日の入りは19時1分です。3日の日の出前には細い月と火星が、28日の未明から明け方にかけては月と土星が接近して見られます。このころの日の出前ということは3時台になるので夜更かしするか早起きするか悩ましい所です。
今年の梅雨は短めで雨量は多めの予報が出ています。豪雨と猛暑が気がかりですが、6月は晴れるとチョウとの出会いも楽しみな季節です。

カノコガ |